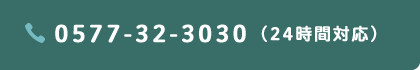よくあるご質問
- HOME |
- よくあるご質問
葬儀についてよくある質問

「こんな時はどうすればいいの?」葬儀に関するよくある質問をご紹介します。
- 私は妻と子ども2人と神奈川に住んでいます。実家のある高山には母親(父親は10年前に他界)がひとりで暮らし、昨年からは養護施設のお世話になっています。万が一の時の心づもりはしておこうと思うのですが、何かと心配です。
三礼は「24時間365日体制」で電話1本でお伺いいたします。葬儀はその家々によってさまざま。経験豊かなスタッフが、親戚の方々も交えてお打ち合わせさせていただきます。
また、もしご自宅への搬送が困難(弔問客を迎えられる状態ではない、電気や水道が使えない…など)でしたら、三礼の安置室へ直接お連れすることも可能です。ご安心ください。
- 現在、東京に住んでいます。高山の実家では父親がひとりで暮らしています。実家の近隣の方が「もしもの時はみんなで協力するから大丈夫」と言ってくださいますが、その反面、ご近所で万が一のことがあったら、今度は自分が手伝わなくてはならないかと思うと大変です。
ご心配、よくわかります。実家から遠く離れてお住まいの方はこういったご心配が絶えません。しかし近年は、葬儀のお手伝いを私ども専門スタッフが代行させていただくことが多くなりました。それによって近隣の方たちには会葬していただくだけで済み、以前より心的負担も軽くなったかと思います。ご安心ください。
- いよいよ母が危篤宣告を受けました。何か用意しておくことはありますか?
まずは何よりあなた様が無理をなさってお体を悪くなさらないようご自愛ください。
葬儀は心づもりができないままに突然訪れることが多いものです。「遺影写真の写真が準備していない」「食事などの準備がいるから、親戚の数を把握しなくては…」などいろいろ戸惑われることでしょう。しかしご心配は無用です。斎壇用の遺影写真はコンピュータを使ってスナップ写真を加工処理するなどして仕上げます。ご準備いただくのは式当日であれば間に合います。また食事の数などについては、親戚縁者が集合されてから皆さんで相談なさったほうがよいでしょう。
いずれの場合も経験豊かなスタッフがアドバイスいたしますのでご安心ください。
- うちは年寄り2人住まいです。もしもの時もご近所に迷惑をかけたくはないのですが…。
ここ数年、「葬儀の手伝いは専門スタッフに代行してもらう」と考えられる方が多いようです。
町内づきあいで葬儀の手伝いをするのはとても大切ですが、実際に「自分が手伝ってもらった分をいつか手伝いで返せるか?」などと考えると悩みはつきません。特に商売を営んでいる方は、通夜と葬儀の2日間休業しなくてはなりませんし、小さなお子さんや病人がいらっしゃる家では留守も心配です。さまざまな事情に応じて専門スタッフがアドバイスいたしますのでご安心ください。
- 家族が亡くなった場合、ひっそりと家族だけでお別れをしたいと思っていますが大丈夫でしょうか?
最近では家族だけで行う「家族葬」のケースが増えてきています。家族葬が一般葬などと違う点は人数の少ない点ではないでしょうか?しかし家族葬には「シンプルでアットホームなお別れ」という利点の反面、「家族だけが満足できる一方的なさよなら」といった批判的な評価もあります。故人と関わりのあった方たちにとって葬儀は、感謝の気持ち遺族に伝えたり、惜別の思いを他の仲間と共有することで自身の気持ちを整理する機会でもあります。
高山では今も地域のつながりが色濃く残っています。長年暮らしていれば、葬儀には近隣の方だけでもかなりの人数の会葬が見込まれるでしょう。また故人が長年続けていた仕事や趣味があれば、家族が知らないお仲間がいらっしゃるかもしれません。家族葬を行うには、そういった方々に「家族だけでひっそりと葬儀を行います」とお知らせする事前の根回しやその後の配慮が必要です。
そうしないと、「最期のお別れがしたかったのに、なぜ知らせてくれなかったのか?」などと、お互いにわだかまりが残ってしまいます。こうした心配事にも専門スタッフがアドバイスいたしますのでご安心ください。
- もしもの時は生まれ育った自宅でお別れがしたいのですが…。
昔は葬儀は自宅で、というのが当たり前でした。しかし時代とともに生活環境が変化し人付き合いも多様化、葬儀の時に多くの会葬者を収容しきれなくなりました。そこで地域の集会場や寺院が葬儀場として使われるようになったのです。
故人と縁のある方達とのお別れのことを考えると「駐車場はどうしたらよいか?」「通路に行列ができ、騒音やゴミなど近隣へ迷惑がかかるのでは?」「事故や天候による会葬者への負担は?」などの心配もあります。また自宅を葬儀場にすることは、予想以上に大変なことです。もしもの時はお住まいの広さ、近隣の状況、駐車スペースなどをご考慮の上、ご家族の思いを大切にしながら私ども専門スタッフがサポートさせていただきますので、ぜひご相談ください。
- 香典の相場はいくらぐらいでしょうか?
香典は「自分と相手の関係」「自分の状況」「地域の習慣」などが影響されます。また香典は「もらったら返す」という「お互い様文化」の上にも成り立っています。高額すぎる香典や、むやみやたらと配り歩くようなことは控えたほうがよいでしょう。
ご参考までに、ある金融機関が発表したデータをここにお知らせします。
●自分に対して相手が…
「勤務先の上司」…5000円
「勤務先の同僚」…5000円
「勤務先の部下」…5000円
「親戚」…1万円~10万円
「友人・知人の家族」…5000円
「隣人」…5000円
これ以外にも、自分が独身で両親が健在の場合は隣人や親戚に対して香典を準備する必要はないでしょうし、職場や趣味の会など自分と同じ立場の人が他にもいるようであれば相談して申し合わせをするのもよいでしょう。
- 香典はどのような入れ物に入れるとよいのですか?
かつて仏教式の葬儀には自分が焼香するためのお香を持参しました。しかし時代とともに変化し、遺族を金銭的に助ける意味合いもありお香の代わりに現金を持参するようになりました。現金は人に贈り物をするときの習わしに従って紙で包み、表書きをします。
一般的には市販されている香典袋を使います。
さまざまなタイプがありますが1万円まででしたら封筒タイプがよいでしょう。
地域の習慣によってさまざまですが、通夜〜忌明けまでの間は「御香典」、忌明け以降は「御佛前」でよいかと思います。生菓子などは「御供」とすれば間違いないでしょう。またキリスト教(プロテスタント)式の場合は「御花料」、神道式の場合は「御玉串料」とします。
- 葬儀参列の服装はどうしたらよいですか?
葬儀は突然のことです。仕事先で訃報を知ることもあるでしょう。そういった場合、喪服の準備が間に合わないこともまります。あまり華美な服装は葬儀の場にふさわしくないでしょうが、遺族に簡単に詫びるなどすれば「取るものもとりあえず葬儀にかけつけた」という気持ちを理解してもらえるのではないでしょうか?
会葬者は黒の略礼服が無難です。それが間に合わない時はダーク系のスーツでも大丈夫です。
派手なアクセサリーや香水は控えたほうがよさそうです。また仏教式の葬儀には数珠は欠かせませんのでご注意ください。
- 2つの法事をまとめて行うことはできますか?
亡くなられた日を命日といいます。例えば1月23日に亡くなられた方は毎年1月23日を祥月命日(しょうつきめいにち)、1月以外の23日を月命日(つきめいにち)といいます。
月命日や祥月命日には、お寺さまが自宅を訪問し、お経をあげます。一般的に命日は家族で営まれます。家族だけではなく、親戚や近隣も集まって営む祥月命日の仏事を「年忌法要」(ねんきほうよう)といいます。
年忌法要は一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌・・・と続きます。比較的短い期間に複数の年忌法要が重なる可能性もあります。その場合、家族だけではなく親戚や近隣を招くとなるとできるだけ一度ですむようにしたいのは本音でしょう。
本来法要は「その人ひとり」のために営まれるものなので、事情が許す限りそれぞれに段取りするのが好ましいといわれます。しかしやむをえない場合は合斎(がっさい)といい、2つ以上の法要を一度に行うことが可能です。いずれの場合もまずはお寺さまに相談してください。